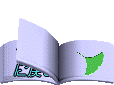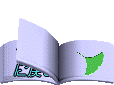浪費とは?
浪費と言えば、まず思い浮かぶのがお金の使いすぎでしょう 世に自己破産
が増加していることは既に知られています 実際のお金ではなくクレジット
カードを持つと、まるで金の生る木でも持ったかのような錯覚に陥って、欲
しい物だけではなく、たいした欲しくない物までも買ってしまいます
ここでは欲求よりも消費することが目的になるという逆転が起こります
つまり欲しい物を手に入れるために購入するのではなく、買うこと、そして
それを消費することが目的化されて快楽になるのです
G.バタイユは、戦争を含めて無駄な消費が氾濫することを放蕩と称しました
手段と目的の逆転
元々は栄養を摂って生命を維持するために食べるのです。その食べることを
快にするために食べ物をおいしいと感じる味覚が発達して食欲をそそるので
す もちろん視覚や臭覚も関与しています
食欲という手段が生命維持という目的よりも優位に置かれて、おいしい物を
食べることが目的になることがあります と言うよりも豊かな社会ではその
方が当たり前になります
豊饒は次に食欲を自己目的化して、食べたいという空腹感があり、食べると
おいしいという快から離れて、食べ物を胃袋に入れることが欲求の対象にな
り、肥満を怖れて嘔吐するという反復を強います
この時食べるという行為は快から不快へと転じますが、止められないという
特徴を持っていて、快楽の極のような位置に在るのです
こうして過剰な消費があちこちで起こっていますが、破綻することで道徳的
に悪にされます 借金で破産する、過食と嘔吐で苦しむ上に家計が破綻する
こうして浪費=悪とされます
最近は地球のエネルギー源としての石油資源の枯渇と環境破壊に対する危惧
が省エネを善としています ポルシェに象徴されるスポーツカーが衰退して
エコカーが流行る時代は、個々人にも省エネを善にしているでしょうか
躁状態は、共同体の結びつきが強かった時代には、そのエネルギーが共同体
と一体となって凝集したのでしょう そこでは個のエネルギーが共同体へと
結集し、そこからまた個へと還元されるという回路ができているのです
しかし共同意識が薄まった昨今では、その凝集力を失って個々人の中で虚し
く消費されるのです 多弁、多動、過干渉と並んで浪費が問題行動になりま
す 貯蓄が失われるどころか膨大な借金を背負うことも稀ではありません
目が覚めた時に、どうしてあんな物を買ったのだろうと後悔します ここで
は買う目的である商品の価値は薄まって、消費すること自体が目的になって
いるからです
高揚気分はスポーツカーの快感
上記の事態は躁うつ病という病であることは皆さんお分かりでしょう その
中には「うつ病の慢性化」の項で書いたように、軽躁状態という逸脱を見ない
うつ病の中の一過性の状態と考えるのか、躁うつ病と考えるのか微妙なかた
も居ます いずれにしても一種の高揚状態の中で活動します
そしてやがて訪れるうつ状態がひどくなります
こうしたことを反復している内にうつ状態が慢性化することがあります
躁うつ病のかたは一般的にうつ状態の方が長いのですが、その時期の苦しみ
が慢性化してきます 単極性うつ病のかたは晴れの日が減って、曇りと雨の
日が多くなります
こうしたかたの一部は、熱中する自分にアイデンティファイしています 熱
中性が共通する病前性格ですが、そうした時に自分らしさが味わえるのです
そして満足のいく達成感を味わいたいのです そのことが共同体の利益と密
接に結びついていた時代の文化の後継者です
特に躁うつ病のかたは「乗り」を大事にします しかし周りの多くの人々は、
お祭りという限定期間にしか「乗り」ません
人がいい、義理堅い、律儀、自己犠牲的なかたたちですが、熱中性と完全主
義を伴うことが多いのです そしてともすれば共同体と調和せずに空回りし
ます
この性格は典型的には執着性格と言って、躁うつ病に多い病前性格ですが、
薄まった形で、うつ病の患者さんの中にも居ます
お金には限りがあって、使いすぎるのは悪という道徳観があるのに、過労に
なるほど頑張るのは善であるという世の中の道徳観があるので目立ちません
多くのかたは、私が過活動を抑えると反発します 調子が良くて頑張ってい
るのに何故誉めてくれないのか、何故注意されるのか 今までそんな者は居
なかった 頑張って非難されるとは、何と割りの合わないことか
精神科医ですら、そんなことを言った者は居ない云々と
ある医師は、躁うつ病の治療は患者さんの一生、ライフサイクルという長期
的な時間の中で観るべきで、短期的な失敗にこだわるのは良くないと言いま
すが、慧眼です
しかしやはり一度考えてみてほしいものです
地球のエネルギーと同じで、個人の生気的エネルギーにも限りがあるのです
この価値観の転換は簡単ではありません
何故なら高揚状態でしか味わえない快、そうした気分でしかできない前進と
いうのがあるからです
お金にも生気的エネルギーにも限りがある
しかしそうしたことがうつ病を慢性化するとしたら不幸です お金と同じで
生気的エネルギーにも限りがあって、そうした意識の中で、浪費をしないこ
とが善であるという道徳観もあって良いのではないでしょうか
道徳観は、矛盾を含む懐の深いものが良いと思います
社会は無理を求めます 国際競争は過密で高度な労働を強います そして得
た収入を消費することを善と勘違いさせる文化です 消費が景気を良くする
からです
しかし過剰な消費は破産に導かれます
過活動を善とするのは、同調性を旨とするうつ病のかたには無理もない道徳
観なのですが、一度考えてみる価値があるのではないでしょうか
お祭りに象徴される共同体のエネルギーの凝縮が、個のエネルギーを充填し
ていたとすると、今の時代は、個と共同体の絆を分離したことによって、高
揚意識を単なる病的な躁状態としたのかもしれません
個のエネルギーを、空中に虚しく消費する空回りの回路の中に嵌め込むと、
共同体からの見返りがありません そうした関係の中で、個のエネルギーは
充填されずに空中に放散するのです 彼らを、こうした回路を作り出した時
代の犠牲者と観ることもできます
しかし犠牲者で良いわけがありません
そのためには、限りのあるエネルギーの消費をコントロールするリズム(武
田信玄の風林火山のような短距離決戦型から長距離持久戦型=マラソンへ)を
獲得する時でしょう
このことは急性精神病からの回復過程にも言えます 一気に自立しようとす
る志向が痛ましい結果になることを多く観てきました
蚕は繭に包まれ外界から保護されて、一見静止しているような時期を過ごす
からこそ、みごとなシルクを紡ぐのです 中井久夫氏が、急性精神病の回復
に必須な充分な休養の時期を繭に例えた比喩は美しい