どんがね
どんがねは、漁師さんの料理です。朝獲れたての鮒は夕方には骨まで柔らかくなり、晩酌のつまみになったのです。
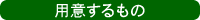
・鮒(ガンゾと呼ばれる小鮒がベスト) ・・ 3尾
・青ねぎか青じそ ・・・・・・・・・・・ 適宜
・酢味噌
みそ ・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
酢 ・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
からし ・・・・・・・・・・・・ 小さじ2
みりん ・・・・・・・・・・・・ 少々
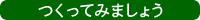
①鮒の鱗を取る。
②魚が大きい場合は3枚におろし、骨を取って小切り
する。
③冷水(氷水)できれいに洗い、水気を切る。
④酢味噌をつくり、③と混ぜ合わせる。
⑤さらしねぎ(または青じそ)を載せて、できあがり。

たっぷりの酢味噌であえて、味をなじませ、
大皿に盛るのが漁師さん風
|

鱗を丁寧におとす

エラに包丁を入れ、内臓を取り除く

魚が小さい時は骨ごとぶつ切りするのが、漁師さん風

魚が大きい場合は、三枚におろして骨を取り、
小切りにする

小切りにした鮒は冷水でよく洗って臭みをとる

よく水を切る
|
鱒めし
鱒めしは、人寄りがあると必ず出された料理です。運動会や寄合い、法事など人がたくさん集まると鱒めしのおいしさも倍増するのが不思議です。
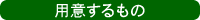
・米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一升
・鱒(中くらいのもの) ・・・・・・・・・ 一尾
・にんじん(小) ・・・・・・・・・・・・ 一本
・合わせ調味料
しょうゆ ・・・・・・・・・・・ 1カップ
だしの素 ・・・・・・・・・・・ 20グラム
みりん・酒 ・・・・・・・・・・ 各少々
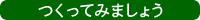
①にんじんは粗い千切りにする。
②鱒をきれいに洗う。
③鱒を熱湯の中で、丸ごと煮て(頭からおいしいだしが出る)、骨と皮を取っておく。
④③に①と合わせ調味料を入れ、米を炊き上げる。
⑤鱒が子持ちなら、炊き上がる直前に子を入れる。
⑥充分蒸らせて、できあがり。

誰もがおいしい鱒めしのでき上がり
|

鱒はきれいに洗う。さっとウロコを取る

ひたひたのお湯で煮て、だしを取る

煮上がった鱒は、トレイの上で骨と皮を取り除く
|
