海津集落の共同墓地にある通称「清水の桜」は、水上勉氏作の小説「櫻守」の中で、桜の移植や世話に一生を尽くした主人公の弥吉が死後その桜の下に葬ってほしいと遺言した、いわれのあるエドヒガンザクラです。樹齢300年を超え、高さ16メートル、幹回り6.4メートルの堂々たる巨桜は、江戸時代加賀藩主が上洛の際何度も振り返ってその美しさを愛でたことから「見返りの桜」の別名があり、滋賀県指定の自然記念物にもなっています。
この桜の樹勢が、車の排気ガス等の環境変化により年々衰え、枯死の心配さえ出始めたことから、町では平成5年に樹木医金森亮太郎さん(浅井町在住)にお願いし、大がかりな再生手術による手当てを施していただきました。お蔭で清水の桜は何とか一命を取り留め、今では毎年かつてのように見事な花をつけるようになりました。
この時に、あわせて日本の桜名所百選に選ばれている「海津大崎の桜並木」も診ていただいたところ、大崎桜も同様に危険な状態にあると診断されたことが、「美しいマキノ・桜守の会」が誕生するきっかけとなりました。
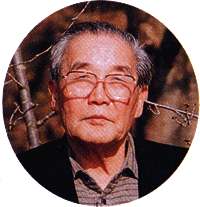 桜守の会会長の内田廣さんは、「地元の者は、桜は放っておいても勝手に咲くものと思っていましたが、金森さんの話で、人が手入れしないと弱っていく生命なんだと気づきました。清水の桜は金森さんが定期診断してくれるので、それじゃあ大崎の桜は我々が守ろうということになったんです」と話されています。 桜守の会会長の内田廣さんは、「地元の者は、桜は放っておいても勝手に咲くものと思っていましたが、金森さんの話で、人が手入れしないと弱っていく生命なんだと気づきました。清水の桜は金森さんが定期診断してくれるので、それじゃあ大崎の桜は我々が守ろうということになったんです」と話されています。
大崎の桜並木は、昭和11年に大崎トンネルが完成したのを記念してマキノ町の前身である海津村が植えたものですが、そのきっかけとなったのは、さらに遡ること5年前、当時滋賀県修路作業員として大崎への県道の補修にあたっていた宗戸清七さん(当時37歳・百瀬村(現マキノ町)在住・故人)が、つらい作業の合間に自費で購入したソメイヨシノの若木を植えたことです。愛着のある湖岸の道に何かを残したいと黙々と植樹を続ける宗戸さんをやがて村の青年団が手伝うようになり、徐々に桜並木は伸びました。
宗戸さんと青年団が植え、海津村が植え、地元の人々や観光関係者が補植を続けたお蔭で今では4キロメートル600本にのぼる桜の花のトンネルができあがるまでになったのです。
桜守の会は、現在会員約230名。テング巣病や折れ枝の除去、苔取り、施肥、除草、清掃など年2〜3回実施される保全作業には、地元海津をはじめ観光協会、商工会などの町内の会員のほか、遠く京阪神からも趣旨に賛同する会員の皆さんが、たくさん参加されています。
桜守の心を通じて、地域の人々とふるさとを離れた出身者、琵琶湖の下流で生きる都市生活者たちの心がひとつになろうとしています。

|
