「不老泉」(ふろうせん)
お地蔵さんが出られた蔵内の自噴井戸より命名。
「恵迪吉」
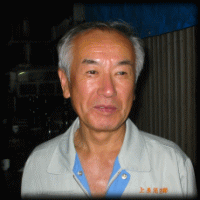 「迪(みち)に恵(したが)へば吉。」 「迪(みち)に恵(したが)へば吉。」
明治35年に富岡鐡斎が太田の蛙声庵で書いた言葉です。
これは、中国の古典「書経」にあり、
「人の道を歩めば吉となり、道に逆らえば凶となる。
怠ることなく、荒むことなく、ひたすら勉め励むべし」
と帝に王の道を説いた中の言葉です。
当時は、向学の地として栄えていたため、多くの文化人が太田の地を訪れたようです。
蛍雪文庫や柳原学校など歴史にその名をとどめています。
しっかりと丁寧に酒を造ります。 ※当社のキャップにも印刷しています。
社長 上原忠雄
上原酒造の日本酒のできるまで
(1)玄米
日本で作られている約200種の水稲のうるち米のうち約90種が日本酒の原料として使われています。
特に酒造に適したものを酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)と呼んでいます。
上原酒造では、山田錦、たかね錦(にしき)、玉栄(たまさかえ)、亀の尾(かめのお)、
吟吹雪(ぎんふぶき)など契約栽培の高品質の酒米(さかまい)を使用しています。
(2)精米
玄米の外側の酒造りに不要な成分をけずりとる工程です。
上原酒造では 県下で3ヶ所しかない最新の精米機(右写真)で
ゆっくりと丁寧に米を磨きます。
急いで精米すると温度が上がってしまい、デンプン質が傷むのです。
 
写真左:上原酒造精米機
写真右:精米中のようす
▲ページTOP
(3)洗米(せんまい)
精米されたばかりの米は摩擦等により水分を失っているため、一定期間(2〜4週間)置いたのち、枯らして失われた水分を戻してやります。
糠(ぬか)を除くために水で洗います。
吟醸酒の場合は米洗機ではなく、ザルなどで手洗いをしております。
(4)浸漬(しんせき)
洗米後、さらに米の吸水率の調整を行います。さらに吟醸酒ではストップウォッチで秒単位の吸水時間をみます。
(5)蒸米(むしまい)
お米は生のままでは、デンプン質は消化分解しにくいので、40分から1時間程度蒸して糊化デンプンにします。
蒸す道具を「甑(こしき)」といいます。
蒸した熱い米を手早く均等に冷ます作業(放冷・ほうれい)をして、
麹室(こうじむろ)や仕込みタンクへ運び込みます。
 
写真左:甑(こしき)で米を蒸しているところ
写真右:蒸しあがった米をさましているところ
▲ページTOP
(6)製麹(せいきく)
蒸米に麹菌(こうじきん)(モヤシと呼ばれています)を散布し、保温して麹(こうじ)を造ります。
一麹二酉元三造り(いちこうじ、にもと、さんつくり)と言われるように、
麹造りは日本酒を造るうえで最も重要で難しい工程です。
※酉元(もと)は本当は1文字ですが変換できないのでこのように書いています。お許しください。
(7)酒母(しゅぼ)(酉元・もと) ※酉と元が合わさり1文字で「もと」なのですが、読み取ってくれません。
お酒を発酵させるための優良酵母を純粋に大量培養したもの。
酒母タンクに麹・蒸米・水・酵母を加えて造ります。
酒母は酒母は雑菌に汚染されないように多量の乳酸を含有しています。
上原酒造では現在でも蔵に棲み付く天然酵母を呼び込み、そして育てる伝統的な山廃仕込を続けております。
この手法で酵母を育てる山廃仕込を行う蔵元は全国でもほとんど見られません。
この山廃仕込みで醸された酒は独特の深みを持つ濃醇な味わいとなります。
▼山廃仕込みについて詳しくはこちらへ
(8)もろみ
麹と酒母ができると本仕込みと呼ばれる もろみ仕込みに入ります。
麹+酒母+蒸米+水→もろみ
一度に蒸米や水を仕込むと、雑菌に対する抗菌力の役割を果たす乳酸や、純粋に培養された酵母濃度が薄まり、雑菌に汚染される危険があるため、3回に分けて徐々に増量していく「三段仕込」の手法がとられております。
現在はもろみの仕込はホーロータンクが使用されていますが、
上原酒造では2004年から木桶を使ってもろみを発酵させる「木桶仕込」にも取り組んでいます。
▼2004年「木桶仕込み」のようすはこちら

写真:活発に発酵中のもろみ(「亀亀覇」)
▲ページTOP
(9)圧搾(しぼり)
成熟した もろみを圧搾することを「上槽(じょうそう)」
あるいは「槽(ふな)かけ」とも言います。
一般の酒は「ヤブタ式」などの自動圧搾機を使います。
特定名称酒等は、もろみを袋に入れ、
昔ながらの木槽(ふね)で搾ります。
上原酒造では、手間を惜しまない
「木槽天秤しぼり(きぶねてんびんしぼり)」を続けています。
酒に優しいこの方法で酒造りをする酒蔵は全国でも珍しくなりました。
手間ヒマは 機械搾りの三倍以上、搾れる酒は八割五分程度という、
効率の悪いものですが、そのぶん酒の味は格段によいのが特長です。
▼「木槽天秤搾り(きぶねてんびんしぼり)」詳しくはこちら
 
写真左:もろみを布の袋に詰めているところ
写真右:木槽(きぶね)に重ねられたもろみ
 
写真左:木製の天秤棒で重石をつけ搾ります。
写真右:木槽(きぶね)下のふなくちから酒が流れ出ています。
(10)滓引き(おりびき)
搾りたての酒には、まだ残存物があり、白濁しているので10日ほどタンクで静かに寝かせます。
すると残存物が沈殿し、タンクの下にたまってきます。
タンクの底から少し上にある「呑み口(のみくち)」から、上澄みを抜きます。
これを滓引きといいます。
(11)濾過(ろか)
滓引きが終わり、清澄になった酒にもまだ微細な粒子が混じっています。
それを更にフィルターなどを通して色や雑味を取り除きます。
最近では、酒本来の味を生かす目的で、無濾過で出荷することも増えました。
(12)火入れ
濾過された酒は、微生物や酵素がまだ生きているので、酵素の破壊と微生物の殺菌をするために、60〜65度に加熱します。
火入れの方法には、パネルヒーターを通して加熱する方法、
蛇管(じゃかん)とよばれる細い金属の筒を通し、湯せんする方法、
瓶詰め後、直接お湯につける瓶燗(びんかん)などがあります。
上原酒造では酒を大切にするため、瓶燗(びんかん)を中心におこなっています。
お飲みになるときも、燗は熱燗より ぬる燗をお勧めします。
▲ページTOP
(13)貯蔵
火入れした酒は出荷時の瓶詰めまで貯蔵タンクで熟成させます。
15〜20度で貯蔵します。
上原酒造では、コンテナ7基を使用し、吟醸酒や生酒などの品質を保つのに
理想的な氷温で貯蔵しています。
(14)瓶詰め
出荷時期を迎えた酒を検査し、酒によっては加水したり、再度火入れ殺菌したりしたのち、
瓶詰めして出荷します。
一般的に出荷前には酒の味の調整が行われることが多いのですが、
上原酒造では、味の調整の必要のない酒造りを心がけています。
出荷も酒を大切にしてくださる業者さんにだけ扱っていただいています。
※日本酒造りの工程の説明は、「日本酒大全」(日経新聞社)を参考にさせていただきました。
|
![]()
